J-PARC News 第242号
■ プレス発表
新たな原子系「多価ミュオン※イオン」の観測に成功
-宇宙観測検出器が捉えるエキゾチック原子の世界 -(6月19日)
原子の中で複数の電子が取り除かれると、「多価イオン」と呼ばれる高い正電荷を持つイオンが生成されます。そのうち、原子核に電子と負ミュオンが同時に束縛された「多価ミュオンイオン」の観察では、周囲の物質からの電荷移行反応を抑制することが重要で、原子数密度が小さく気圧が低い気体標的を用いて実験を行う必要があります。しかし、原子数密度を下げると多価ミュオンの生産量も減少してしまいます。
そこで、物質・生命科学実験施設(MLF)のミュオン基礎科学実験装置(Muon D2)の低エネルギーミュオンを用いて多価ミュオンイオンの生成量を増やしました。さらに、宇宙X線観測などの高精度分光を目的として開発された超伝導転移端センサーマイクロカロリメータ(TES)を導入しました。そこから放出する多価ミュオンイオンの電子特性X線エネルギーを精密に測定した結果、多価ミュオンイオンに束縛された電子の個数およびその量子状態までを識別して観測することに初めて成功しました。
多価ミュオンイオンはこれまでにない全く新しい種類の原子であり、基礎科学の観点から非常に興味深い系です。また、本研究により確立した多価ミュオンイオンの高精度分光技術は、負ミュオンの新たな応用展開を広げるための礎となることも期待されます。
※ミュー粒子のことを「ミュオン」または「ミューオン」と表す。
詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/06/19001563.html
■ KEKが提案した研究開発3件が経済安全保障重要技術育成プログラムとして採択(6月13日)
高エネルギー加速器研究機構(KEK)が提案した素粒子ミュオンを使った構造物イメージング技術に関する研究開発が、標記プログラムの実施先として採択されました。実施期間は2024年8月から2029年7月末までです。採択された課題は以下の通りです。
1.ミュオン特性X線を用いた元素分布の可視化技術の開発
2.超伝導転移端マイクロカロリメータを用いた宇宙線ミュオンによる超高分解能元素分析
3.小型で人工的に高強度のミュオンを生成するコア技術の開発
また、他の研究機関の提案でKEKの研究者も参加する課題も3件採択されました。
詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/06/13001555.html
■ J-PARC安全の日(5月23日)
2013年5月23日、ハドロン施設で放射性物質の漏洩事故を起こし、地元の皆様をはじめとする多くの関係者に、ご迷惑、ご心配をおかけしました。J-PARCでは安全について再考することを目的とし、毎年、この時期に「J-PARC安全の日」を設けています。
今年は5月23日に開催し、ハイブリット方式により374名が参加しました。午前中は安全情報交換会として、各セクションから「火災事象を踏まえた取り組み」に関する情報交換を行いました。午後は安全文化醸成研究会として、まず安全貢献賞の表彰等を行い、その後、「機内食の安全管理~見えないリスクの低減に向けて」という題目で、日本航空株式会社 商品・サービス開発部の川野亜紀氏、藤尾智宏氏、岩本正治氏が講演を行いました。そこでは、機内で安全な食事を提供するために、迅速かつ正確な作業が必要であることが述べられ、具体例が紹介されました。最後に記録映像「J-PARC放射性漏えい事故-科学的側面を中心に-」を上映しました。
J-PARCでは二度とこのような事故を起こすことがないよう、職員一同が安全を最優先に研究活動を行うため、今後もこの行事を毎年続けていきます。

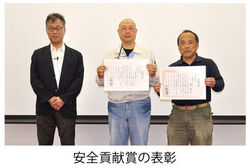
■ 中高生がJ-PARCのミュオンビーム実験に挑戦(5月5~6日)
加速キッチン合同会社の探求支援を受ける4名の中高生が、J-PARC MLFのミュオン基礎科学実験装置「Muon D1」でミュオンビーム実験を行いました。中高生がJ-PARCでビーム実験を行うのは、今回が初めてです。
女子学院高等学校の松下千穂里さんは、2024年に日本人高校生として初めてCERNでビーム実験を行ったSakura Particlesのメンバーの一人です。今回は、CERNで性能評価を行った2次元ビームモニタを用いたビーム実験のさらなる検証を行いました。名古屋大学教育学部附属中・高等学校の川道かのんさんと淺野颯良さんは宇宙線ミュオンの速度をTime of Flight (TOF)法で観測する探究に取り組んでおり、ビームライン上の前方検出器と後方検出器の2つの検出器間の距離を変えながら、ミュオンの到来時間差を測定しました。東京学芸大学附属高等学校の青野真優さんは加速キッチンで「学校の天井の厚みを宇宙線で計測する」探究活動を行っており、自作コンクリートを用意して、その前後に検出器を設置してビーム実験を行いました。
詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/05/23001516.html
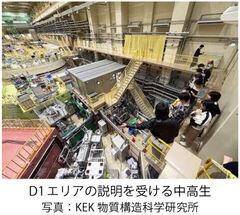
■ 記者向けJ-PARC・KEK施設見学会(6月16日)
「ここまで進んだハイパーカミオカンデ プロジェクト! ニュートリノビーム発射側から見るニュートリノ実験の歴史と最新情報」と名付けられた報道機関向けのニュートリノ施設見学会を開催しました。今回の見学会では、新聞社やテレビ局などのメディアだけでなく、フリーランスのライターやカメラマン、サイエンス系YouTuberなどにも門戸を開いたため、幅広い分野から25人が参加しました。
午前中はつくば市のKEKで、世界初の長基線ニュートリノ振動実験(K2K実験)の遺構として、ニュートリノビームラインや水-チェレンコフ型の前置検出器を見学しました。午後のJ-PARCのニュートリノモニター棟では、地下のオフアクシス検出器やINGRID(オンアクシス検出器)を間近で見学しました。特にオフアクシス検出器はメンテナンス中ということで電磁石が開いており、換装されたばかりの新観測装置を見ることができました。また、東海村内に建設中のハイパーカミオカンデ中間検出器の建設現場も見学に行きました。
この見学会の様子は全国的に幅広く報道され、世間からのニュートリノ振動実験への関心の高さが、あらためて示されました。

■ J-PARCハローサイエンス「空から降り注ぐミュー粒子で古代の謎を探る」(5月30日)
素粒子原子核ディビジョンの藤井芳昭氏が、ミュー粒子を使った古墳の内部調査「宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト」について紹介しました。
東海村の指定文化財である「舟塚古墳群2号墳」は、6世紀につくられた権力者の古墳であるとされていますが、古墳の内部構造は謎のままです。そこで、宇宙線ミュー粒子を使って古墳内部を透視し、非破壊で石室を探すプロジェクトが2年前から始まっています。児童生徒を主体とするこの文理融合プロジェクトは、世界的にも珍しく、多くのメディアに取り上げられています。
小中高生の参加者は、様々な分野の専門家から考古学、郷土の歴史、放射線や素粒子、測定器の原理などの講義を受け、自分たちの手でミュー粒子測定器を組み上げました。その後、地図上で考えた測定器設置候補地を現地で確認し、昨年10月に最適と思われる場所に設置して測定を始めています。解析結果が出るのはもう少し先になりますが、どのような結果が得られるのか、ロマンが広がります。
藤井氏はこの活動を通して、「子供たちに郷土について関心を持つと同時に科学の面白さも知ってもらいたい、理科好き・歴史好きに成長してもらえたら嬉しい」と話しました。

■ 研究開発棟見学会(6月2日)
総合研究大学院大学の永田敬学長、山本智副学長を招いて、今年3月に完成した「SOKENDAI共同研究拠点・J-PARC実験機器開発棟(研究開発棟)」の見学会を開催しました。
詳しくはこちら(KEK HP)https://www.kek.jp/ja/topics/202506181700sokendai

■ J-PARC出張講座
小山工業高等専門学校(6月10日)
小山工業高等専門学校の本科2、3年生130名を対象に、「ミクロの世界を見る加速器の仕組み ~素粒子現象から巨大構造物まで透視するミューオン加速技術~」と題する講演を行いました。本講演は、高専生による小型加速器製作~AxeLatoon(アクセラトゥーン:加速器を意味するAcceleratorと新芽を意味するRatoonに由来する造語)~を主体とした社会連携事業の取り組みとして開催されたもので、講師を加速器ディビジョンの大谷将士氏が務めました。
大谷氏は、加速器の原理から、産業・医療といった広い分野での応用利用についての紹介、J-PARCで人工的に大量生成したミューオンを用いた研究や、最新の技術開発・研究展開について紹介しました。講演後のアンケートには、「加速器の実用例をもっと聞きたい」「今後予想される加速器の使用用途をもっと聞いてみたい」「普段聞かないKEK・J-PARCでの研究内容や研究所での生活など知れてよかった」などの感想をいただきました。

≪お知らせ≫
■ 「J-PARC・原子力科学研究所 施設公開2025」のお知らせ(8月23日)
8月23日(土)、「科学で拓く、明日の世界」と題し、J-PARC・原子力科学研究所が合同で施設公開を開催します。普段は見る事ができない実験施設、加速器などの見学(一部事前予約制)や、サイエンスカフェ、実験工作教室、キッチンカーなどもあります。是非お越しください!
詳しくはこちら(J-PARC・原子力科学研究所 施設公開2025特設ページ)https://j-parc.jp/OPEN_HOUSE/2025/

J-PARCさんぽ道 59 -小さいものの大きな旅-
J-PARCの最寄り駅であるJR東海駅には、今年も南の国からつばめがやってきました。つばめは他の渡り鳥のように群れを作らず、単独で何千キロもの海を渡ります。昆虫などの獲物を捕らえる時や猛禽類などから逃げる時は、時速200㎞近くで飛ぶことができます。つばめの体重はわずか20グラム、500円玉3枚分にもなりません。この小さいつばめがこれだけの持久力と瞬発力を持っていることは、われわれ人間からみると、驚異に思えます。
J-PARCが人工的につくり出す極めて小さい粒子、ニュートリノもほぼ光速で飛んでいき、ほとんどは295km先のスーパーカミオカンデの巨大な水槽をも通り抜けて宇宙空間へと旅立ちます。
これから続く猛暑の中、こんな小さなものを見つめ、壮大な世界に想いを馳せるのも、悪くないかもしれません。


